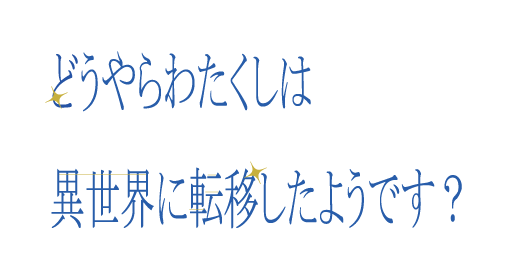復讐するためには準備が必要だった。
あたし吉岡ヒナタは借りた教室の鍵で、一足先に三階の空き教室を訪れていた。
そこは普段使っている教室と何ら変わりはない。
ただ、しばらく使われていなかったため、無造作に置かれた机や椅子はうっすらとホコリをかぶっている。前方には壁時計があり、時刻はちょうど17時を示していた。カーテンは外されており、窓から差し込む光はすごく眩しい。
あたしは制服のポケットから二台のスマホを取り出した。事務所から支給された仕事用とプライベート用のだ。
汚れが一番マシな机を選び、撮影する場所を決め、仕事用のスマホを配置する。
あくまで一般人の顔は映らないようにカメラの位置を微調整して、何度も確認を重ねる。
失敗は許されない。今日彼らの前であの動画を生配信で公開する。
次に『ヒナチーチャンネル』の生配信の設定を行った。これで自分のスマホで遠隔操作すれば、自動的に配信始まる段取りになっている。更に続けて自分のSNSを全て使用して最大の告知する。
『今日は生配信でみんなにわたしの恥ずかしいところを見せちゃいます!!!18時ぐらいからからやるよ!期待して待っててね!』
あたしはそこまでの準備を終えると大きく息を吐き出した。
一週間で百万なんて我ながら呆れてしまう。駆け出し女優のあたしは養成所のレッスン料、スキンケア代でギリギリだ。
そんな大金、ヤンキーもどきとキモオタクにできるハズがない。なんなら10万円も無理だったかもね。
呑気に考えながら適当な椅子に腰かけ足を組む。もちろん、これもホコリまみれだったのでキレイにしてからね。
生配信する理由は二つある。
一つ目は『恥ずかしいところ』なんて言っておけばファン以外も勝手に食い付く点。
二つ目はさらに生配信はやり直しができない点だ。そこが狙い目だった。
そう配信事故に見せかけてあのVtuberの動画を映し出すの。
「ごめんなさい!!間違えました」って本当は違う動画を見せるハズだったんだって、目元に涙を浮かべてあげる。
好きなんでしょ?こういうステレオタイプの女が。
いいわよ。特別に演じてあげる。
あたしはそれだけでいい。
噂は噂を呼び、やがて燃え上がるのだろう。それでいい。たちまち、注目の的になるでしょうね。
Vtuberなんて所詮はこんなものだと世間の夢を覚まさせてあげるだけ。
自分のスマホをさわり、『吉岡ヒナタ アンチ』で検索する。そこにはいつものようにあたしを責める文字の羅列が並んでいた。
最初はあたしが出演したドラマの感想を目的だった。
だってふつう気になるでしょ?
マネージャーからはエゴサーチはSNSだけにしておけと言われた。
あたしは最初、それがどういう意味なのか分からなかった。
だからかな。言いつけを守らず検索してしまった。あたしが悪かったのかな。
深淵(しんえん)を覗いた先にあったのは闇。
【吉岡ヒナタ】は匿名性をいいことにネットの掲示板で叩かれていた。
『ヒナチの配信見た?アレは酷かったよなwww』
『ドラマから分かってたことだろ』
『リアルで見たことあるけど、ブスだったわ』
これ以上は見ていけないと全身が警鐘を鳴らす。だけどスクロールする手は止まってはくれない。一つ残らず見てしまった。後悔した。けど、もう遅い。
それから毎日、書き込みが増えていないか確認する癖が抜けなってしまった。見れば必ず後悔するのに、見ないと安心で眠れない。矛盾してる。そんなことあたしが一番よく分かっている。
頭には書き込みがちらつき、上手く演技することができなくなっていく。それに比例してスレッドは苛烈さを増していった。
そうして、とある書き込みがされた。
『生身の人間でやるなよな。まだVtuberの方がマシじゃね?』
その言葉を見たとき、あたしの心の何かが糸みたいにプツンと切れた。憎悪は、これで二度目。
あたしは努力に努力を重ねてここにいる。
過酷なダイエットだって、厳しすぎるくらいの生活リズムだって、発音練習も演技指導も全部やった。あたしは全てを晒しながら活動している。ストーカー被害も、刺されそうになったこともあった。
それなのに、なんで、なんで、バーチャルに身を包んだだけの一般人ががもてはやされるの!?
あたしはあたしがこれ以上傷つかないように良い子ちゃんの仮面を被った。何も見ないようにしていた。
なのに、あいつが動画を見せてきた。
身体中の血液が沸騰しフラッシュバックする。また、邪魔をするの?
安全圏にいるあなたたちが!これ以上あたしの舞台に上がってこないでよ!!!!
もうなんだっていい、もうどうだっていい。
引きずりだしてやる。手元の動画に映るVtuberが誰かなんてどうだっていい。
廊下側から聞いたことのある男子生徒の荒げた声が聞こえてきた。
現実に引き戻されたあたしは、スマホに18:00と浮かび上がったを確認すると、スカートのポケットに忍ばせた。
やってきたのは一人。それも息を切らしたヤンキーもどきだけだ。
その瞬間、あたしは勝ちを確信した。隠したスマホを気が付かれないように力一杯握りしめる。
「待った!」
現れた声の主によって、あたしは信じられない光景を目にすることになる。