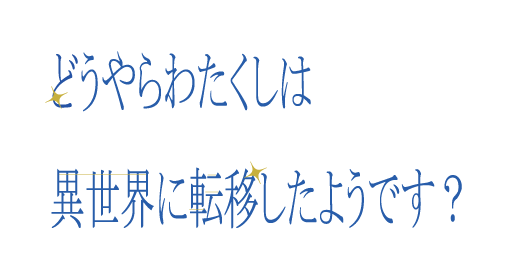一刻も早く。ヒナタを止めねば。
竜胆モモが消えてしまう。動け! 動け! 俺の足!
「せいぜい、特等席で大好きなVtuberが崩れていく様を見てなさい」
ヒナタは前を向き、カメラの方へ足を踏み出す。
オレンジ色の光が教室に差し込み、背中を向けられた姿に沿って影が伸びていく。
その光景があの日と重なった。
「ごめん、今日はモモの配信があるからまた今度な!」
「……そうだよね。急にごめん。また今度ね!」
全てが夕日に染まったあの日を。
髪を右耳にかけ、無理に作った笑顔を。
二度と振り返ることのなかったその背中を。
あれはきっとヒナタなりのSOSのメッセージだったはず。
だって、ヒナタは《《嘘をつくとき》》髪を右耳にかけるのだ。
「あ」
そのとき、口から飛び出した言葉は懇願ではなかった。それは謝罪だった。
ヒナタの背中越しに、俺は喉が張り裂けそうなくらい大声で叫ぶ。
「あの日、助けられなくてごめん!!!」
あまりの大声に驚き、思わずヒナタは振り返る。
俺は膝をつき、頭が地面に減り込むくらいの土下座をした。
「今更、謝っても許されないことだと分かっている!」
「だから! これが俺の覚悟でけじめだ!!」
頭を上げてカバンをひっくり返すとザラザラと竜胆モモのグッズが床に散らばっていく。
俺は手ごろなサイズのフィギアを一つ取り――乱暴に床に叩つけた。
激しい音と共にそれは無残にも粉々に砕ける。破片が波紋のように広がる。
細かい破片が刃となり、右手に鋭い痛みが走る。血だ。
「はぁっ!? 何やってんのよ? それはあんたが一番大切にしてきたモノじゃないの!?」
「これで許されるなんて思ってない! だからお前の気が済むまで俺は壊し続ける」
次のフィギアを手に取り、同じように床に叩きつける。手の先から全身に振動が伝わっていく。痛みはさらに強くなる。破片が右頬を掠り、血が流れる。波紋はさらに大きく広がる。
喉が張り裂けたっていい。血が流れたっていい。この手が使い物にならなくたっていい。
大切な人を蔑《ないがし》ろにして――
「そんなんで、竜胆モモファンを名乗れるか!!!」
三つ目のフィギアを手に取ったとき、一瞬ひるむ。
これは竜胆モモ一年目生誕祭の……。頬に温かいものが流れたような気がした。
関係ない。俺は大きく振りかぶった。
前から硬いもの同士がぶつかるような耳をつんざく音が聞こえた。
ぼやける視界に細い手が飛び込んできた。その両手は震えながらも振り下ろそうとした手を必死に抑える。
「……ばっかじゃないの。もういい」様々な感情の混ざり合った声が耳元で揺らいだ。
「けど――」
「もういいから」座り込むヒナタもまた頬が濡れていた。
吉岡ヒナタはいいやつなんだ、本当に。
何も言わなくなったヒナタを気まずく思った俺は、助けを求めるようにすぐるを見る。しかし、すぐるは口パクと指差しで何かを必死に伝えようとしている。
『は、い、し、ん』
「はいしん?」
ゆっくりとすぐるの指先へ目を向ける。
赤いランプがヒナタの肩越しから光り、こちらを捉えている。
「あ」最初は間抜けな一言。それが波となり一面に広がっていく。
「ああああああああああ!!」
見事に配信にのった俺は別の事件に巻き込まれることになる。
だけど、それはまた別のお話し。